
011~015 まで記録していきます。生活の知恵、座右の銘、哲学としてご参考ください。
011 無用には大きなはたらきがある
車輪は、三十本のやが中央のこしきに集まっている。
そのこしきの中心には何もない穴があいているから車輪がうまくはたらくことになるのだ。
粘土をこねることで器はできる。
その器の中はなにもないところがあるから器としてのはたらきができるようになる。
戸や窓をくりぬくことで家としてできあがる。
家のなかに何もない空間があるからこそ、家としてのはたらきがある。
このように、何かがあることによって役に立つのは、何もないことがあるからこそ、そのはたらきができるのである。
012 ぜいたいく、刺激的なものを追うとおかしくなる
五つの色を使ったきらびやかな色彩が人の目をくらます。
五つの音を使ったいろいろな音楽が人の耳をおかしくさせる。
五つの味を交えたおいしい料理が人の味覚を損なわせる。
馬を走らせ狩猟するとしう趣味は人の心を狂気にさせる。
手に入れにくい財賃は人の行いをおかしくさせる。
だから「道」と一体になっている聖人は、人々の腹をいっぱいにすることに努めて、目を楽しませるようなことはしない(生活を重んじて、ぜいたく、刺激的なことでごまかさない)。
したがって、あちらの目を捨てて、こちらの腹を取るのだ(華美なことを捨て、基本の生活を重視するのだ)。
013 欲望などより、自分の身体が一番大切である
世の人々は寵愛(ちょうあい)を得ては胸ときめかせ、屈辱を受けては、胸をふさがせる。
そして寵愛(ちょうあい)屈辱とかを大きな関心事として、自分の身と同じもののように考えているようだ。
どうして寵愛(ちょうあい)とか屈辱に一喜一憂するのであろうか。
寵愛(ちょうあい)はくだらないものだ。
それなのにそれを手に入れられるかと心配し、失うと不安でいる。
こうした状態を寵愛(ちょうあい)と屈辱にびくびくと心配、不安でいっぱいだというのである。
ではどうして寵愛(ちょうあい)とか屈辱(あるいは名誉とか財産)などの得喪を大きな心配事としているのか。
それは自分の欲望に執着しているからだ。
自分の欲望への執着がないと、何も心配することはないのである(だから、大切なことは自分の身、生命の根本を大切にすることである)。
だから、天下を治めるということより、自分の身を大切にする人にこそ天下をまかすことができるのだ。
自分の身を愛する人だからこそ天下をあずけることができるのである(外部の余計な欲望から切り離され、大切な我が身を扱うように、天下を大切に扱うからである。)
014 古くから万物の資源(「道」)が今も私たちを支えている
目をこらしても見えない。
それを「夷」という。
耳をすましても聞こえない。
それを「希」という。
手でさぐっても捕れえられない。
それを「微」という。
これら三つのものは、つきとめようとしてもそれはできない。
いわゆる「道」というものは、三つのものが一つのものに混じり合ってできているのだ。
この一つに混じり合ったものの上は明るいわけではなく、それの下は暗いわけではない。
果てしなく続き名づけようもなく、結局は万物が名づけられる前の根源的な無の世界(「道」)に戻っていく。
これを「無状の状」(姿のない姿)、「無物の像」(形のない形)、「恍惚」(おぼろげなもの)という。
前から迎えてもその頭は見えず、後からついていっても、その後ろ姿は見えない。
古い昔からの道をしっかりと守って、それによって現在のことをとりしきれば、古くからの始まりを知ることができる。
これを「道紀」(「道」の法則という)。
015 満ちていっぱいにならないから、どんどん新しく生まれてくる
昔の立派な士(「道」に通じようとしている人)というのは、微妙な優れたはたらきで奥深いところに通じていて、その深さは計り知れない。
だが、強いてその姿を述べてみたい。
ためらいつつ冬の冷たい川を渡るときのように慎重で、念には念を入れて四方の敵を恐れるように注意深くて、きりっとしていて威儀を正した客のように立派で、なごやかで素直なことは氷が溶けるときのようであり、素朴であることはまだ削っていないあら木(加工する前の純木)のようであり、広々として無心でいることは谷のようであり、何でも併せ呑むことは濁り水のようである。
誰が濁ったものを静かにして、だんだんと澄ましていくことができるのか。
誰が安定しているものを動かしてものをだんだん生み出していけるのか。
この「道」を保っている人は、満ちていっぱいになることを望まない。
いっぱいになることをしないからこそ、だめになってもまた新たにできてくるのだ。
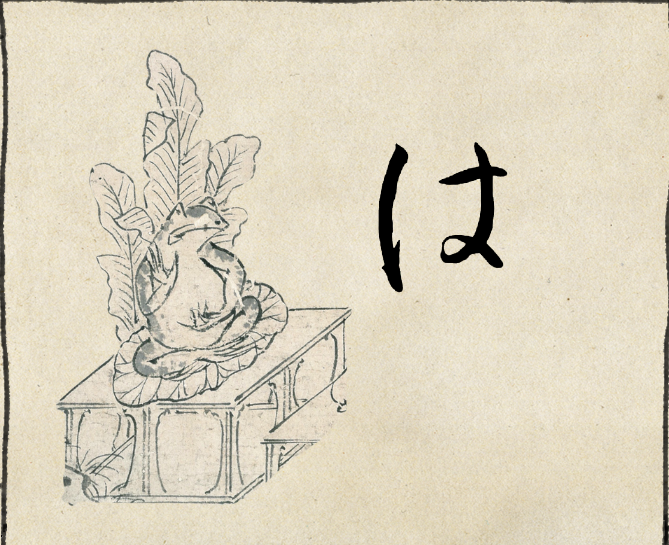
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18c9bb53.3ee3d3a7.18c9bb54.4a77be26/?me_id=1213310&item_id=19423197&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9110%2F9784416519110.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9110%2F9784416519110.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

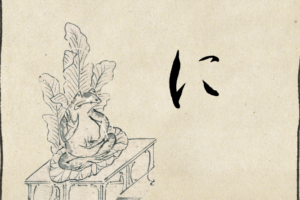







コメントを残す